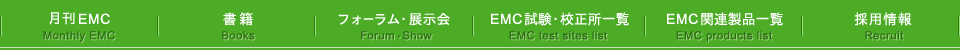開催概要
| 会期 |
2025年10月21日(火) |
| 受講形式 |
会場受講:当日現地 池袋サンシャインシティワールドインポートマートビル
WEB受講:配信期間(予定)
2025年10月27日(月)10時~2025年10月29日(水)18時まで
|
| 分野 |
EMC/パワー半導体/WPT/モータ/ポイントクラウド/CMOS/カルマンフィルタ/高速デジタル回路設計 |
| セッション |
- 第31回 EMC環境フォーラム 総合セッション
- 第31回 EMC環境フォーラム 技術セッション
- 第26回 スマート設計技術フォーラム 技術セッション
|
◎ 第31回 EMC環境フォーラム 総合セッション会場のみ
| 開催日時 |
2025年10月21日(火) 16:30~18:30 |
| 会場 |
池袋サンシャインシティワールドインポートマートビル5階
東京都豊島区東池袋3丁目1-3(アクセスマップ) |
| 定員 |
120名 |
| 総合司会 |
- 次世代EMC研究会 会長、
公益財団法人鉄道総合技術研究所 前会長、
東京大学 名誉教授 正田 英介氏

|
| テーマ |
EMC関連学会の現状と近未来 |
| 講演 |
- 第一講演:IEICE EMCJの現状と戦略 - 企業連携とアジア地域展開について
- 第二講演:電気学会電磁環境技術委員会の現状と近未来
- 第三講演:IEEE EMC Societyの紹介
- 第四講演:EMC Europe - 欧州におけるEMC研究の中核シンポジウムの歴史と現状
|
| 受講料 |
テキスト代 3,000円(税別)/名
(技術セッション受講者、招待者、月刊EMC購読者は無料) |
| 備考 |
「会場」のみの開催となります(WEB配信はございません) |
◎ 第31回 EMC環境フォーラム/第26回 スマート設計技術フォーラム 技術セッション
| 開催日時 |
2025年10月21日(火)9:00~16:00
(セッションにより多少変動あり) |
| 会場受講 |
会場:
池袋サンシャインシティワールドインポートマートビル5階
東京都豊島区東池袋3丁目1-3(アクセスマップ)
定員:
各セッション50名
|
| WEB受講 |
WEB受講は後日配信となります
配信期間(予定):
2025年10月27日(月)10時~
2025年10月29日(水)18時まで |
| 運営委員長 |
東京都市大学 名誉教授 徳田 正満 氏 |
| 副委員長 |
東京大学 教授 大崎 博之 氏 |
| セッション一覧 |
◎第31回 EMC環境フォーラム
会場のみマークのセッションはWEB受講はございません。
セッション5
- 航空機システム電動化とEMC
- [チェアパーソン] 秋田大学/秋田県立大学 電動化システム共同研究センター センター長 榊 純一氏
◎第26回 スマート設計技術フォーラム
会場のみマークのセッションはWEB受講はございません。
|
| 受講料 |
【会場受講】
- 優待受講料 46,000円(税別)/名
- 一般受講料 52,000円(税別)/名
【WEB受講】
- 優待受講料 28,000円(税別)/名
- 一般受講料 33,000円(税別)/名
|
- セッションは変更になる場合がございます。
- 優待受講料は、2025年8月31日までにお申し込みの方(会場受講限定)、講師のご紹介者、月刊EMC購読者、前回フォーラムを受講された方が対象となります。
セッション詳細・お申込み
参加ご希望セッションのチェックボックスにチェックを入れて「お申込みフォーム」ボタンを押してください。
受講料・お申込み方法について
- 技術セッション受講料(税別)には [テキスト代・昼食代] を含みます。
|
通常申込み |
早期申込み |
月刊EMC購読者
講師のご紹介者
前回フォーラム受講者 |
| EMC環境フォーラム総合セッション |
3,000円※技術セッション受講者、招待者、月刊EMC購読者は無料 |
| EMC環境フォーラム/スマート設計技術フォーラム技術セッション(会場) |
一般受講料
52,000円 |
優待受講料
46,000円 |
優待受講料
46,000円 |
| EMC環境フォーラム/スマート設計技術フォーラム技術セッション(WEB後日配信) |
一般受講料
33,000円 |
- |
優待受講料
28,000円 |
| お申込み締切 |
2025年10月末 |
2025年8月31日 |
2025年10月末 |
- 総合セッションは、本フォーラムの技術セッション受講者(会場/WEB)及び講師のご紹介者、月刊EMC購読者の方は無料となります。
- 技術セッションの優待受講料は、2025年8月31日までにお申し込みの方(会場受講限定)、講師のご紹介者、月刊EMC購読者、前回フォーラムを受講された方が対象となります。
- 会場受講をご希望の方で、2025年9月1日以降にお申し込みの方、またWEB受講をご希望の方は、お支払い方法でクレジット決済を選択された場合、優待受講料の適用外となりますのでご注意ください。優待受講料対象の方は「請求書払い」をご選択ください。
- 全て税抜き表示です。
- 参加ご希望セッションの受講形式を選び、「お申込みチェックボックス」をチェックして下さい。↓
- 「お申込みフォーム」ボタンを押し、お申込みを行ってください。↓
- 弊社よりお申込み完了メールがお手元に届きます。
振込先情報が記載されておりますのでお振込みをお願いいたします(請求書払い/クレジット決済を除く)。
請求書払いの方へは当社より請求書をお送り致します。↓
- お振込み確認後、メールにて「受講票」をお送り致します。
WEB受講(後日配信)の方は、受講URLとパスワードの記載をご確認ください。↓
- 会場受講の方:受講票をご持参の上、当日会場へお越しください。
WEB受講(後日配信)の方:配信期間内に、受講票に記載の受講URLにアクセスし、パスワードを入力後、ご受講をお願いいたします。